
『とるにたらぬ話』の収録短編②
歩いた。茹だるような暑さの中をただひたすら歩いた。何時間も歩いているのにまだ何処にも辿り着く気配はなく、それでも足を止める気にはならなくて歩き続けている。暑い。八月の殺人的な陽射しはとうに傾き始めているけど、川の水面に反射する西日が容赦なく照りつけてくる。
背筋を、額を、汗が伝う感覚が気持ち悪い。頬の傷に汗が染みてチリッと痛んだ。
「あのさっ、耕田、もうちょいゆっくり歩かない?」
「あ、悪ぃ」
隣を歩く葉山は同じ中一とは思えないほど細っこい。汗でベトベトな俺も大概な姿ではあったが、彼はもっとヘニョヘニョのクシャクシャな状態で必死に歩いていた。暑すぎない? 夏、と今気づきましたみたいな顔で抜かしている。
「体力ねぇなぁ」
「足の長さでしょ。身体がデカい方が優しさ見してよ」
「大して身長変わんねーじゃんか」
「運動部入っときゃよかったかなー」
「無理だろ」
まあね、と返しながら葉山はへへっと眉を下げてみせた。わざとらしい奴。その取ってつけたような柔らかな笑顔は暑さ以上に俺をイラつかせた。
葉山に合わせて歩調を緩める。束の間の会話は途切れ、再び俺たちは無言で歩みを進めた。歩き始めた時より周囲の人間がだいぶ減った気がする。川沿いとはいえ、この暑さの中ウォーキングやジョギングに精を出す人もいないだろうから、もしかしたらみんな夜を待っているのかもしれない。夜になって、通行人が増えたら少し困るなと思った。まあ、今更どうしようもないけど。葉山はそんなこと全然考えてないんだろうと横を見やる。左隣を歩く葉山はさっきより多少は落ち着いたように見えたが、まだ少し肩で息をしていた。彼が急いで着いてこようとしなくていいように、もっとのんびりと、葉山の気持ち後ろを追うくらいのテンポで歩く。
「次コンビニあったら寄ろーぜ」
パッとこちらを振り返った葉山の顔が輝く。中学生とは思えないほど幼かった。
「耕田、神?」
「冷てぇもんでも買おうぜ。あと普通にエアコン浴びたい」
「わかる、コンビニって寒くていいよね」
ちょっとだけ葉山の背筋が伸びた。希望が見えてきたらしい。まだまだ当分歩くことになるだろうが大丈夫だろうか。
引き返す予定はないし、それは葉山も同じだった。
だからこそ俺たちは、暑いだの疲れただの時々口に出すわりに歩みを止めなかった。時々喋って、あとはひたすら黙って歩いた。
セミの声だけがやけに耳に響いた。あまりにも夏らしく晴れた空には、やっぱり嘘みたいに夏らしい大きな雲が浮かんでいた。
「ねー、耕田」
葉山が振り返らずに呟いた。
「ちゃんと死ねんのかなぁ、僕たち」
葉山の背中に視線が止まる。細っこく、頼りなく、ちょっと猫背な背中。自分と同じようにTシャツが汗で張り付いている。
「じゃなかったら何しに行くんだよ」
葉山は振り返らない。
馬鹿みたいに眩しい夏の夕暮れのことだった。
午前中からボコボコに殴られて気分は最悪だった。親父が昼前に起きているとこなんてここ一年ぐらい見たことがなかったから油断していた。なんか知らんけど、機嫌も普通に悪かったんだろう。加えて、俺が少しいい気分だったのがよくなかった。もっと言うと、少しいい気分でお上品な朝ご飯でも食べちゃおうかしらなんて思っていて、鼻唄混じりに素麺なんか茹でちゃって、ついでに付け合わせに細〜い卵焼きなんか作ってたのが悪かった。もう多分、何もかも全部よくなかった。
まず「うるせぇ」から始まって、俺が「あ、起きてたの」と返す「の」の時点で頭を掴まれていた。途中、「誰の金で飯喰ってると思ってんだ」というテンプレ台詞の後に「飯の前に感謝の一言ぐらい言いに来いよ」と怒鳴られたことだけ覚えている。起こしたってどうせキレるのに。そう思った以外には他に何の言葉も理解できなかった。何の言葉も記憶には残らなかったので、とりあえず朝から鼻唄混じりに料理するのはやめておこうと思った。
「いってぇ〜!」
コンビニの前のポールに腰掛けて、買ったばかりの消毒液を雑に頬の傷にぶっかけると信じられない痛みが走った。消毒液って初めて買うけど意外と高いのな、なぁんてことを呑気に考えながら片手間でやってはいけなかったらしい。顔はもっと大切にしてやらねばならん箇所のようだ。普段は腹やら肩やら時々背中に打撃を喰らうことが多いから大体は青痣になる。今日は珍しく一発目から顔で、運の悪いことに親父の爪が食い込んで血まで出た。派手な顔にされてしまったもんだ。もしかしたら、そういう意味で親父も夏休みモードなのかもしれない。最悪だ。
口ん中は切れて血の味になったし、なんだかんだで素麺は食べられなかった。せっかく茹でたのに。んで、今は消毒液に痛みつけられて涙目で悶絶中。
そんな可哀想な俺に声を掛けてきたのは、入学してから一回も話したことのないクラスメイトだった。
名前は知っていた。明らかに変わり者って雰囲気で、クラスで絶妙に浮いていたから。嫌われているとかではなくて、ただただ全然馴染んでなかった。同じクラスである以外の接点が浮かびそうにない男だったが、そいつの言葉はそんな俺の頭ん中をさらりと裏切った。
「耕田、もしかして耕田も夏休み嬉しくない仲間?」
「え、なにそれ。なんか他にもメンバーいるやつ?」
仲良しグループみたいなやつか?
「いや、耕田もそうなら僕を合わせて今んとこ二人」
なんだそれ。急に話しかけてきて一言目に言うことか。しかもメンバーいないのかよ。言いたいことは多々あったが、夏休みがちっとも嬉しくない点は事実なので今のところ加入決定ではある。
「お前も夏休みキツいんだ」
そう答えたのは理屈じゃなくて、直感めいた何かが「同じだ」と俺に囁いたからだった。
「だいぶキツいね〜」
まず毎日家にいるしかない、と諦めの混じった戯けた声で葉山は言った。
その通りだった。学校がなくなると家にいるしかなかった。毎日活動がある厳しい部活にでも入っておけばよかったと思うけど、そんなのは仮入部届に親のサインが必須だと知ってとっくの昔に諦めた。遊べる場所も金もない。中途半端な田舎で朝から晩まで暇を潰すのには限界があった。できるだけ波風立てないように寝起きして生活するわけだけど、夏休みが始まって一週間も経てば「家に存在している」それだけで目障りだと奴が怒鳴る理由には十分だった。
「窒息するよな、自分の家なのに」
そのまま死ねたらいい。心が死んだらその瞬間、絶望で心臓が止まればいい。そしたらもっと単純に、もっと楽に生きられる。
隣いい? と葉山が訊いた。窮屈になるなぁと思ったけど、立たせたまま話すのは忍びないので横にズレてやる。気を遣った隙間を空けて葉山は俺の隣に腰掛けた。
「その顔、どうしたの」
「あぁ、親父」
「そっか」
なんでコイツにそんなこと言わなきゃいけねぇんだとは思いつつも、変に言い淀んで大袈裟に取られたくなかった。多分相手も同じ感覚を持っていて、なんでもないことのように返事をされた。
「僕はお母さんにそんなボコボコにされることないんだけどさ」
さっきより少し低いトーンで葉山が言う。視線は明後日の方向に放られていて、汗が伝う白い頸だけが目に映る。炎天下で、やけにヒンヤリとしてみえる素肌だった。
「前はもう歩けないばぁちゃんの世話一人でやっててさ。仕事とかもしてたんだけどさ」
ここ何年かはもう全然。どうにもなってなくてさ。葉山の言葉は淡々としていて、静かで、隣にいるのに遠かった。
「頭おかしくなっちゃったんだと思うんだよ。お母さんさ、起きると泣いてるか魂抜けちゃってんの。ほっとくと死んじゃうから、危なくなったらいつも止めてる」
これが昨日のやつ、と葉山が半袖をめくって指を差す。色白な腕に真っ赤なみみず腫れが数本走っているのが見えた。
「どう? 元気出た?」
「出るわけねーだろ」
「あ、そう?」
葉山の喋りには不思議と不快感はなかった。いつもこんな風に、至って穏やかに話すことを心掛けているんだろう。だから、クラスで浮くんじゃねぇの、とは口に出さなかった。代わりに気になったことを訊いてみる。
「親父は?」
「僕ん家がヤバすぎていつの間にかどっかいった、のかな」
「じゃあ、俺ん家と同じだな。いつの間にか母親いなくなった」
今は毎日殴る人と毎日殴られる人だけ。そう戯けて付け加えてみたけど葉山は別に笑わなかった。ちらっと確認するような視線が送られただけ。何見てんだ、こら。
「夏休みヤバすぎだな」
「夏休みヤバすぎんね」
葉山の眉が下がった。ヘラッとした嘘くさい笑顔。癖なんだろう。
「まだ一週間も経ってないのにさ。すっごい長く感じない?」
「あと三週間近くあるっていう事実がヤバいよな」
「毎日ばあちゃん世話してさ。包丁持って死にたがる人毎日必死に止めて、その包丁使って料理して」
その声は笑っているようで、泣いているような、それでいてどこか空っぽだった。
「もう頭おかしくなるよ」
しかもお母さん誰かと会話してんだよ、脳内で。
葉山が自虐的に笑ってみせた。やっぱり俺も笑うことはできなかった。
何のために朝起きて、どうして今日も生きていて、何が楽しみで明日が来るのかわからなくなる。気なんてとっくに狂っていて、息の仕方も傷の痛がり方もいつからかずっと思い出せない。人生が一分一秒と食い荒らされていくのを他人事みたいに眺めながら、どうして今トドメを刺してくれないんだと叫んでいる。
十二歳。誕生日が来たら十三歳。俺たちは無力だった。
「死にたくならない?」
「なるよ」
「でも馬鹿みたいな話なんだけどさ、一人じゃそんな勇気出ないんだよね」
「わかるよ」
同じ温度を感じた。それは吐き気がするほどドクドクと熱く、息もできないくらいに冷え切っていた。葉山と初めて視線が交差した。何かを期待するような、それでいてこの世の何にも期待なんかしていないような凪いだ瞳。きっかけは意外とこういうもんなのかもしれない。それもいいな、と思った。限界だと音を上げたって誰に責められることもないように思えた。
コンビニの駐車場には突き刺すような太陽の他に俺たち二人だけだった。まるで秘密でも打ち明けるみたいに視線を逸らして呟いた。
「じゃあ、お前、俺と死ぬか?」
答えは一つに決まっていた。
「全財産と長袖のパーカー持って、歩きやすい靴で集合な」
待ち合わせの時間にその日の午後六時半を指定すると葉山は普通に「今日!?」と驚いていた。先延ばす意味あんのかと訊くと、一瞬だけ考えて「まぁないね、今日にしよう」とあっけらかんと返ってきた。
それからは暑すぎるとか歩くペースがどうのとか時折会話はあるものの基本的には黙って歩いた。強すぎる西日はゆっくりと息を潜め、ほとんど夜が空気を浸食していた。
「っていうか、なんで死ぬ為にこんな歩かされるわけ」
訊かれてないから言わなかったけど、ここまで汗びっしょりになるまで歩かされれば知りたくなるんだな。大体一時間半ぐらいか。要らん知見が増えてしまった。当然といえば当然だけど、葉山は不満そうだった。
「いや、せっかく自殺するからよ。自殺の名所でしよっかなって」
「え、なに。今から怪談すんの?」
しねぇよ。葉山が不審人物でも見るかのように眉間にシワを寄せる。お前こそなんなんだ。
「別にふざけてるとかじゃなくて。乙川をさ、ずーっと遡ってくと裏山に続いてるらしくてさ」
裏山というのは何故か地元の人間からそう呼ばれている山のことだ。別に何の裏でもないし、そもそも裏山という規模じゃない。普通にデカい謎の山。普段は特に行こうとも思わないちょっと遠くの山。でも、ここら辺に住んでる人なら当たり前に毎日見てる。どのバスに乗ったら辿り着くのかは今も知らないままだが、乙川を上流に向かって行くと裏山に辿り着くという噂を聞いたことがあった。
「裏山って言えば、小学生の頃自殺の名所で有名だったじゃん?」
「全然知らないけど。何小でそんなの流行ってたの」
「北石小だけど。え、聞いたことない?」
裏山は広く、手つかずの場所も多い。特に夏場は熊出没に注意して遊びに行かないように。川の上流は非常に透明度が高く一見すると水遊びにもってこいだが、水深が深く流れが速いので一度入ってしまうと大人でも簡単にはあがれない。夏休みは裏山には近づかないようにしましょう。
「学年集会で言われなかった?」と尋ねると「そんな魅力的な学年集会ないよ」と葉山は呆れた口調で言った。学校からの注意喚起は児童の間でいい具合に尾鰭がつき、盆踊りの時期にはすっかりと怪談に様変わりしていた。死にたい人は裏山へ。ちっちゃい田舎のお手軽な樹海扱いだった。
「もしかして本気であそこまで行く気ぃ?」
顔を歪めて葉山が前方を指差す。指の先にはいつも見てるより少し近い裏山が顔を覗かせていた。そんな嫌そうな顔をしつつも葉山が足を止めることはなかった。
「死ぬなら、できれば確実に死にたいじゃん」
「まあね」
「透明度が高くて深い川ってことはさ、そん中きっとすげぇ綺麗だと思うんだよ」
「それで?」
「最期の最期に一番綺麗な景色見て死にたいなって」
自分で言いながらちょっと恥ずかしくなってきたのに葉山に「耕田、ロマンチストじゃん」と笑われてムカついた。
「あとは普通に別企画『本当に乙川は裏山に続いてるのか』を明らかにしようと思って」
一体何が面白いんだか、葉山はまだ笑っていた。さっきまで夕陽に照らされて赤らんでいた顔が今はもう夜に溶け始めていた。街灯の光を受けてぼんやりと浮かんでいるみたいだった。
「面白いからその検証乗った」
葉山がニヤリと笑顔を作ってみせる。多分、俺も釣られて少し目を細めた。
「お気に召したならよかった。死ぬまで歩くぞ」
「熱中症で死んだら手間省けるけどねぇ」
そんな軽口を叩きながら俺たちは歩いた。ただひたすら歩いた。あの山に沈んで、もう二度と浮かんでくることがないように。
腹減らねぇかという話になった。
当たり前だ。歩き始めてからお互い飲み物以外は口にしていなかった。歩みを進めるにつれてコンビニやファミレスに出会う間隔は広くなってきている。ここらで最期の晩餐に興じておくのもありだな、と。
何を食べるか。それは結局、互いの懐事情に訊いてみる他なかった。一応は昼間に会った時に全財産持ってこいと告げておいたが、葉山の金のなさには感じ入るものがあった。
「2,746円」
「全財産よ?」
「うん。だから全財産。頑張って貯めたんだよ、2,746円。なに、耕田そんな金持ちなわけ」
えぇ、言いづらいよ。頑張って貯めた2,700円の話の後に俺の全財産の話できねぇよ。俺まあまあ普通にあるよ。葉山の無垢な努力に一瞬言葉を失いかけたが、気を遣われたと思ってほしくなくてとりあえず会話を続行させる。
「いや金持ちじゃねぇけど。お前、小遣いとかもらったことない感じ?」
「基本はね。ノートとか上履きとか買った後のお釣りは貰っていいことになってる」
お小遣いって基本みんなあるやつなのと葉山が訊くから、家によるだろと適当に返す。
「耕田の全財産は?」
「32,000円と小銭400円ぐらい」
「すっごー。耕田ん家はお小遣いあるってこと?」
葉山が目を輝かせて訊いてくる。お小遣い、まあそういうことになるのかもしれない。それでも、ちっとも心が躍るような金じゃなかった。
「母親がたまにポストに金入れに来んの。親父、絶対見ねぇの知ってっから。隠して貯めた」
親父は最低な奴に違いなかった。だけど家に二人きりで取り残されたんだとわかった時、母親も大概だったんだと悟った。
親父の苛立ちは母に向き、俺にも向いた。家族は親父の所有物でそのどちらにも親父は手を上げる権利があった。でも母は別に弱い人でもなかった。だからこそ、家庭が破綻するや否や早々に家に寄りつかなくなった。返って来る日が少しずつ減った。親父はその怒りを何故か俺にぶつけた。帰って来ないのは別によかった。ポストに明らかに俺に宛てた金が入っているのを見た時、なんて馬鹿なことを期待して封筒を開けてしまったんだろうと自分に失望した。
母は家には帰って来れるのに、俺を連れて一緒に逃げようとは思わなかったのだ。
もう迎えに来ることはないんだと知った。5,000円ぐらいずつ、多いとは言えない頻度で舞い込む金はできるだけ節約して貯めた。
「逃げ切れたと思って一度も会いに来ないのと中途半端に手ぇ出してくるの、どっちが酷いんだろ」
「比べるもんじゃねぇだろ」
「まあ、今更ね」
金はないよりあった方がいい。結局それだけの話。
「ま、じゃあ、そゆことだからファミレスはやめてコンビニにすっか」
「ファミレスって高いの?」
「っていうより、コンビニの方が贅沢感ある買い物できる」
そこから五分ほど歩いた先で葉山を連れてコンビニに入る。九時半過ぎというと客が多いイメージがあったが、意外にも店内は閑散としていた。
サイダー二本。謎のグミ。ホットスナックを端から端まで好きなだけ。脳内シミュレーションで3,000円以内に収めて葉山から700円もらう。
「なあ、アイスも買わね?」
「最高じゃん。買おう」
よく言えば安心感しかないアイスのラインナップ。さすがは中途半端な田舎、定番しかない。でも、結局定番が美味いから問題はなかった。
少し悩んでガリガリ君に手を伸ばした時、同時に葉山がモナ王を手に取る。
「お前、なんかねっとりしたの喰うなぁ」
「いや耕田こそ、サイダー買ったのにまたソーダ?」
フッと二人で笑った。なんか普通に青春してるみたいだった。
会計を済まして店を出ると我先にとレジ袋の中からアイスを引っ張り出す。陽はすっかりと暮れ、歩き出した時のような滴る汗は引いたが、空気はまだじっとりと暑かった。吹く風があったかくて、手足を振るたび水の中みたいにぬるい空気を掻き分けた。
「急げ、溶ける前に喰うぞ」
「絶対ガリガリ君の方が先溶けるからね」
馬鹿みたいに勢いよく食べて、ソーダで溺れそうになった。葉山は食べるのものんびりで、地面のアスファルトに点々と白い跡が滲んだ。
二人で食べたい物を言い合いながらホットスナックを胃に収めていく。最後のチキンを手に取った時、葉山がぽつりと言った。
「今日、晩御飯作ってこなかったんだぁ」
「それが?」
「ばあちゃんたち、大丈夫かなぁ」
そう言いながら天を仰いだ葉山の頭上にはまばらな星空が広がっていた。
「これから死ぬんだから、明日から毎日お前いねぇじゃん」
「まあそうだけどさぁ!」
そう思う葉山が優しい奴なのか、それとも可哀想な奴なのか。俺には解明できそうにないなと思った。
「ちょっとは困ったらいいんだよ、俺らが死んで」
今まで散々寄りかかって。一日一日擦り減らされて。ある日突然いなくなる。ざまあねぇなって笑ってやるか。取り残されて哀れだなって嘆いてやろうか。そしたら葉山の母親は葉山のことを見てくれるだろうか。俺の親父は俺のことを人間だと思い出してくれるだろうか。
「死んだら困ってくれたらいいなぁ、僕」
歩調が気持ち緩やかになる。何かを思い浮かべているのかもしれなかった。それはまだ色が眩しかった頃の思い出かもしれないし、見ることはない未来のことなのかもしれない。葉山は寂しそうでも、悲しそうでも、嬉しそうでも、別になんでもなかった。
「明日にはお母さん、もう死んでたりして」
蝉の声に負けてしまいそうな、気持ちをどこかに置いてきてしまったみたいな声だった。
それでも、歩き続けている。
「もしそうなったとしてもさ、葉山。お前は何も悪くないよ」
なぁ、葉山。夏休みって最悪だな。でもさ、俺、今死ねたら最後の一日はちょっとよかったなって思えるんじゃねぇかって気もしてんだけど。
お前は何を考えてんのかあんまりわかんない奴だから、俺は上手く応えてやれないよ。
もう裏山がだいぶ近づいているのが、見てとれるところまで来ていた。あんなに買ったはずの最後の晩餐はあっという間に消えてしまった。葉山が「僕、友達と外食したの初めてかもしんない!」とご満悦だったので、こっちまで気分がよくなった。
しめて2,718円の晩餐であった。
歩いた。じっとりと蒸したアスファルトの熱を踏み締めてただひたすら歩いた。
こういう日が来るとしたら、きっと一人で歩いているんだと思っていた。どうしたことか今日は隣を仲良くもない変な少年が歩いている。細っこくて、なんか弱そうなのに、意地でも止まろうとかやめようとか言わない。ゆっくり行こうよとは言うけど。
そりゃまぁ歩いてるんだからいつかは着くんじゃねぇかとは思っていたけどさ。
「いやぁ、まさか……」
「ほんとに着くとはね……」
思ったよりかは遥かに歩いた。ほぼ着いてるよなってとこから二時間は絶対歩いた。リュックの中のお茶やら水やらサイダーもだいぶ減って軽くなった。裏山に足を踏み入れるためには単に川沿いを歩いてりゃいいというわけではなくて、ぐるーっと周って初めて人が歩けそうな道を見つけた。おかげで真の目的地である水源は流れる音すら遠のいてしまった。
車の通れそうな山道を数分歩くと葉山が一回り細まった道を見つけた。よいしょっと少し高さのあるその道に葉山が乗り上げながら言う。
「とりあえず、こっから登る?」
「だなー」
幸い、数日間雨は降っておらずギラギラな炎天続きだったので山道は想像より歩きやすい。一応、道なりという言葉に似合うぐらいにその道は形を持っていた。真夜中にこんなところに来たことがあるわけがなくて、二人ともすげぇすげぇと言い合いながら歩いた。もはや川のことは一旦忘れるくらい非日常な冒険にワクワクした。しばらくはその新鮮な景色に心躍り足取りも軽やかだった。
しかしながら、何事も突然気づくものである。
「ちょっと待て。バカ暗くない? 道」
「わかる」
「あとさ、ついでに言うとさ」
「あ、待って、それ僕が言うわ」
めっちゃ疲れたよなぁ!?
二人の声があまりにも気持ちよく重なる。夜の森に声が反響して、変な鳥が鳴いた。おぉ、と肩をすくめ声を落として会話する。
「そうだよな、俺だけじゃないよな」
「いや、僕もこの四十分ぐらいアドレナリン出てて忘れてたんだけど普通にさ」
「足動かんよなぁ」
「あと前見えなすぎ」
「暗すぎ」
こちとら中学生男子。飽きるのが早い、とも言う。それでもかなりの時間歩きっぱなしだったのは事実だ。車道を外れた夜の森に電柱の一本もないというのもまた事実。明らかにもう進めそうにないということは二人とも薄々わかっていた。
そのまま立ち尽くして少しの間が空く。疲れたと一回口にしてみるともう座りたいとか息苦しいとかそういうことしか考えられなくなる。真夜中なのに蝉の声がする。寝ないのかな、蝉……。もう、なんかいっそ。
「一回寝るか」
「よし寝よう」
そこからは「なんか良さそうなとこ見つけたら寝よう」というモチベーションだけで二人とも歩いた。どこで寝ても大して変わらないような気もしたけど、何か拠り所みたいなものが欲しかった。隠れ家みたいな安心の側で眠りたかった。
夜の森は思っていたよりずっと静かで、二人の荒い息の音と蝉の声、バラバラな足音と風で葉が擦れる音だけがそこにあった。
「ここ! いかがでしょうか!」
葉山が声を上げた。デカくてグニャグニャな木が二、三本絡んで横長な壁みたいな形状に変形している。
「最高です! 寝ようぜ」
地面を手足で払って寝心地を整える。お世辞にもいい寝心地とは言えそうになかった。虫除けにと途中で羽織った長袖パーカーが汗でじっとりと重かった。脱いで横になれそうにないので、諦めてそのまま寝転んだ。葉山もそうした。疲労が、一瞬にして眠気を誘う。もう目を開けていられない。暑さなんて気にならないくらい眠かった。
「耕田、もう寝た?」
「おう」
「ふふ、なんか聴こえる。熊かな」
「じゃあ、明日には死んでるかもなお互い」
「生きてるかどうか、明日起きるの楽しみだ」
うん、俺も。答えずに寝返りを打つ。
「耕田おやすみ」
「おやすみ」
おやすみ。そんな言葉、何年か振りに言ったよ。
眉間の辺りがドクドクと脈打っている。熱い。重い。痛い。というか……、
「痒い!」
衝撃で目を覚ましたのに、目が通常の半分ぐらいしか開かない。ここは何処だ。すごくジメジメしている。あと、身体が痛い。ゆっくりと数回呼吸を繰り返す。咽せ返るほどの土の匂いと青臭い匂い。え、森?
次第に意識が覚醒してくると、雪崩れのように昨日の記憶が蘇ってきた。ようやくここが裏山であると理解した。
「死ななかったな……」
起き上がって傍らに目をやると葉山がむずがるような声を上げている。もう起きるな、これ。
とりあえず目を擦りたい。手探りでリュックを手繰り寄せ、まだ開けてない方の水のペットボトルを取り出す。控えめに垂らして手と顔を洗う。ヌルい。飲んだら不味いだろうなと思う。そんな最悪な水だが、洗うと洗わないでは気分が違う。数分前まで顔の中心にあった重たい腫れぼったさは純粋な痒みに変わっていた。
蚊か。虻か。それにしてもマジで
「最っ悪だあ〜!」
馬鹿でかい声をあげたのは葉山だった。
「なんか凄い刺されてると思うんだけど。あ、耕田起きてたの? フッ!」
顔を見た瞬間、笑いが込み上げてきたのはお互いだった。ほぼ同時に吹き出すように笑った。
「え!? ちょっと待って、フハッ、なんだその顔!」
「そっちこそ、ンフッ、なにそれ! アハハッ、腫れ過ぎ……!」
眉間がぼっこりと腫れた俺の顔。向き合うのは下顎から頬を何箇所も刺されて腫れた葉山の顔。
「アハッ、お前っ、バカみたいな顔っ! ハハハッ!」
「耕田っ、フッ、お岩さんじゃんっ、ンフッ、ねぇやめて?」
馬鹿みたいに面白かった。まん丸に腫れたお互いの顔を見てるだけなのに声を上げて笑った。それだけのことが、とにかく楽しかった。
最初はそれだけのことが笑えた。でも、だんだん笑ってること自体がもう面白かった。自分が堪えきれずに笑っているのを見て、葉山も笑っているからまた笑った。途中から別に何も面白くないけど、俺たちは笑うために笑った。身体の内側から絞り出すみたいに、吐き出すみたいに、思いっきり笑いたくて笑った。ただ、笑っていたかった。
耕田、笑いすぎ。涙出てる。
出てねぇわ。お前こそ人の顔見て笑い泣きすんな。
そんな風に、昨日初めて喋った奴と山の中で笑い合ってるのが面白かった。
息もできないくらい、面白かった。
はあー。最後に一つ大きく呼吸する。
「……帰ろっか」
青い風が柔らかく吹いている。
「帰るか」
葉に遮られた陽射しが昨日より少し優しかった。
「身体が痛すぎる」
葉山がクシャッと笑いながら俺を見る。
「最悪だけど布団あるだけマシかもな」
わざと悪戯っぽい目をして返す。
「まあ、マシってことは別にないけど」
だけど、俺たちの歩く方向は何故だかもう決まっていて。一歩、一歩、ゆっくりと、ただ来た時と同じ道を歩いた。
歩いて、歩いて、歩いて。ただひたすら歩いた。全身がバキバキに痛くて、顔があり得ないぐらい腫れてたけど、止まることはなかった。
もうだいぶ陽が高くなった頃、俺たちの旅の相棒だった乙川に再会した。
夏の眩しすぎる太陽が水面に反射して、どこまでも光っていた。眩しすぎて、それ以外のことが割とどうでもよくなるくらい光っていた。
「熊に、襲われなかったね〜」
「遭難とかも別にしなかったな。どっか落っこったり」
「熱中症とかも結局ならなかったし」
「虫に刺されただけ」
「あはっ、ウケる」
まじで一日かけて何してるんだろう。意味がわかんなくて笑える。こんなに歩いて獲得したのは虫刺されだけって。それでも。
「でもこれ、よく考えたら結構奇跡だったんじゃね?」
「ほぼ無傷で歩いてるしね。奇跡か。奇跡じゃしょうがないね!」
「すげぇ、奇跡起きちゃってるわ」
葉山が急にわぁっと声を上げながら川に向かって走り出した。意味がわからないまま追いかけて走った。裏山の中はあんなにしっとりと涼やかだったのに、この道は暑い。一歩駆け出しただけで馬鹿みたいに汗が吹き出す。暑い。眩しい。葉山はあんまり走るのも速くはなかった。追い抜かして、川に一番近いところで止まった。葉山も全力で追ってきて、二人で息を切らす。肩で息をしながら葉山が弾んだ声で言う。
「なんか僕、今めちゃくちゃ叫びたい気分」
いい? と言うから、よくはないけどとは思いつつも頷いた。今が何時かはわからないけど、山に近い田舎には俺たちを見る人影もない。なんて叫ぶの、と訊こうと口を開いた瞬間、
「ざまあみろーーーーー!!!!」
あまりにも気持ちよく晴天の中に響き渡った。強くて、デカい声だった。それは一度も聞いたことのない声だったから、その瞬間葉山のものとは思えなかった。でも、これが多分、葉山なんだと思った。
「それ、何に対して?」
「え、なんだろ。熊、とか?」
「熊……」
あれだけ爆裂に叫んだというのに、葉山はきょとんとしている。
「っていうか、今、この瞬間の僕たち以外の全部に?」
言葉を手繰り寄せるみたいな曖昧さで、葉山が答える。少し、目が泳いでいる。
「なんか、思い通りになると思うなよって」
死にたいとか。死んでやろうとか。疎ましいとか。幸せだとか。思い通りになると思うなよって。あんたの思った通りの都合のいい人生を俺たちが生きていくと思うなよ。ずっと大人しく同じ場所にいると思うなよ。春とか、夏とか、いつも変わらない日常とか。死にたいのに生きてて。もう死んでるのに、まだ生きている。全部、全部、全部、馬鹿野郎、ざまあみろって。期待して、馬鹿をみて。生きているから、心の底から叫んでいる。
「うわ、いいな。俺もなんか叫ぼうかな」
「そうだよ。叫んどきな」
葉山みたいに地球が揺れるほどの大声で叫んでみてぇな、と思った。誰もみてないし。夏休みだし。
すぅーっと大きく息を吸う。夏の灼ける温度が肺に広がる。
「ざまあみやがれ馬鹿やろーーーー!!!!」
最後の一息まで搾り出すように叫んだら、心臓の音で身体が震えた。
「いい叫びだったね」
「それは何目線で言ってんだ」
じゃあ、また、歩こうか。
そう言いあって俺たちはまた歩き出す。暑い。太陽が容赦なく差している。川の水面は俺たちの叫びなんかペロリと吸い込んで、何もなかったみたいに穏やかに光っていた。俺たちはただひたすら歩いた。思いつきばかりのバカバカしくてくだらない話をしながら。
「帰ったら親父ブチギレてたりしてな」
「え、急に笑えない話題出してくるじゃん。リアクション困るって」
「逆にいないの気付いてなかったとかさ」
「まあ、どちらにせよさぁ」
葉山が目を細めて、俺の顔を覗き込む。あの嘘くさい笑顔はもうやめたらしい。
「耕田はなんも悪くないよ」
してやったりって顔。お前、そういう風に喋ったら多分クラスに友達できるよ。
暑い、暑い夏の中を俺らは歩いていく。滝みたいな汗を流して、地球を踏みつけるみたいに歩いている。ただひたすら、時々黙って、時々笑いながら。
「なあ、葉山」
「何?」
「今度また死にたくなったらさ」
「うん」
「そん時はもっと豪華な夕飯喰おうぜ」
「さんせ〜! その時までお金貯めとく」
歩く。来た道を辿ってまっすぐに、来た時とはどこか違う景色を眺めながら。
荒く息を吐き、瞼を汗が伝い、たまには天を仰ぎつつも俺たちはまだ歩き続けている。
夏の空は馬鹿みたいにデカくて、陽射しが何にも遮られることなく俺たちの歩く道を照らしている。
容赦なく注がれるその眩しい光の中を、ただひたすら止まることなく歩いていく。
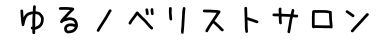
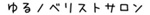
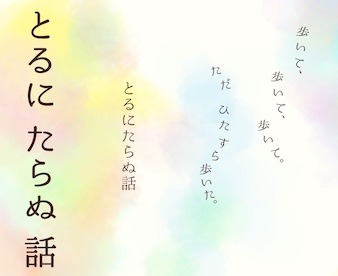
コメント
二作目も読ませて頂きました!
こちらも友情モノですね。繊細な表現の中に純粋な青さが見える、すごく読了感が心地いい作品でした。
二人の環境があまりにかわいそうで、友情深めながらも歩き続けているときは、「本当に死ぬの?」とハラハラしながら見ていました。
でも、二人の環境を考えたら、誰も止めることなどできない。
葉山の「ファミレスって高いの?」「初めて友達と外食したかも!」の台詞が胸に刺さります。こんなことも経験できない中学生の日常って、あまりにかわいそうですね。
最後の最後、二人が強くなって現実に戻ってくれるので、本当に安心しました。
戻っても環境は変わらず辛いかもしれないけど、「死ぬ気」という気概だったり、親友だったり、色々なものを得て強くなった二人は、今までとは違う毎日を創り出してくれそうですね。
爽やかな物語をありがとうございました!
ファミレスのくだりの前後の会話は2人の「当たり前」がどんな状況か伝われ〜〜!!!って思いながら書いていたのでコメントしてもらえて嬉しいです
感想ありがとうございます!