
※サークル「小説を書く会」にて、1時間で創作した小説です。
少し荒い点もありますが、ご容赦下さい。
……………………………………………
カフェのドアがカランと鳴り、やつが入ってきた。
「やー、お待たせ。残業がなかなか終わらなくてねぇ」
そう言いながら、屈託ない笑顔でおれの正面に座る。
セミロングの髪を書き上げ、ふわっと香水の良い香りがおれの前をかすめた。
「おせぇよ」
おれは、思わず目を伏せてしまう自分に気づき、心の中で軽く舌打ちする。
やつの付き合いは、もう1年以上になる。
中学の同窓会で、たまたま会ったやつは、昔は目立たないおとなしいタイプだった。
たまたま隣の席だったから顔見知りという程度だったが、久しぶりに再会したやつは、すっかり大人の色気ただよう女性になっていた。
中学時代は気付かなかったが、よく笑う。
おとなしいながらも、こちらをじっと見てくすくす笑う彼女に対して、なんとも言えないきまずい感情が沸き起こる。
昔水泳部だった彼女は、いまでもきれいなプロポーションを維持していた。
学生時代は知らなかったが、おれと同じでよく小説を書いているということで、一気に話が盛り上がる。
さらに職場まで隣の駅だったということで、それから都合の合うときはたまに仕事帰りにカフェで合流し、一緒に小説を書くことになった。
職場が近いといっても、おれはスーパーでのアルバイト。
やつは・・・大手企業の経理科で、去年は若くして主任に出世した有望株だそうだ。
かわいげのないやつ。
「いやー、疲れちゃったぁ。新人君がとちっちゃって、教えながらデータ直すのが大変だったんだ。パフェ食べないとやってらんないよ~。あとワインもだぁ」
カフェで会ったときは、そんなエリート風な顔は一切見せず、だらっとした表情でメニューを覗き込んでいる。
「仕事ばっかで、執筆進んでないんじゃねぇのか?おれは1週間でガッツリ3万文字進めたぜぃ」
「おおー、やるねぇ!次は1次選考進めるといいねぇ!」
やつは、くくっと笑う。
「てめー、いつも最終選考進んでるからっていい気になるなよ・・・」
「はっはっはっ、まぁ私を抜いて、書籍か目指してみたまえ」
やつは、余裕の表情でばんばんとおれの肩を叩く。おれはいらっとして、やつの腕を払った。
腕を払う瞬間、ふとやつの手とおれの手が重なったのが、なぜこんなに気になるのか。
もやもやしてしまう自分に腹が立つ。
そう、おれの方が作品投稿数も文字数もいつも多い。
いろんな小説を読んで勉強をしている。
なのに、おれは一次選考を突破したことがなく、やつは数十万人が応募する大型コンクールですでに最終選考まで何度も残っているのだ。
なぜ、こんなにへらへらして気の抜けたやつが、おれより評価されるのか・・・
「なーんか、いつにも増して眉間にシワ寄ってるねぇ」
やつが、おれの顔を覗き込む。
「真剣に話の流れを考えてりゃそうなるだろ」
「芥川龍之介にでもなったつもり?私たちが書いてるのはラノべなんだから、私たちが楽しみながら書かなきゃ、読者も楽しんでくれないでしょ」
「うっせぇなー、おれはお前よりも熱心に創作に向き合ってるんだよ」
「熱心だからいいってわけじゃ・・・おっと」
やつのスマホがぶるぶると鳴る。
「メールか?」
「・・・あ、○×社の創作コンクールの合否通知だ・・・」
「おお、最終選考まで残ってたやつだよな?」
このコンクールは、入賞者は書籍化される新人小説家の登竜門だ。
「やばい、ドキドキする。見るの怖いよ~」
「どーせ落ちてんだから、気軽に見ろよ」
「あんた、繊細な乙女の前でよくそんなことが言えるね。ううう、怖いけど、開く!はい!」
やつは、えいっとばかりにスマホをタップして、画面を見入る。
次の瞬間、突然口をふさいで涙目になった。
「・・・落ちたのそんなにショックか?」
「・・・受かってる」
「・・・へ?」
「合格してるよ~」
やつがスマホの画面をおれに見せてくる。佳作の文字がおれの目に飛び込んできた。
佳作だろうがなんだろうが、入賞。
つまり書籍化決定。
つまり、プロの小説家の仲間入りを果たすことになる。
「ううう、やったよ~」
やつはわざわざ対面のおれの席に回り込んできて抱き着いてきた。
やつのうれしい嗚咽が聞こえる。
しかしおれは・・・その嬉し泣きの声が、ひどく耳障りに聞こえた。
「離れろよ・・・」
「へ?」
「離れろって!」
おれは強引にやつを押しのけて、思わず走り出してしまった。
たまらなく、嫉妬心がおれの心を支配した。
外に出て、カフェの壁にもたれかかる。
都会の喧騒が、やけにおれの心を揺さぶった。
やつが応募した作品は何だっけ、どこの投稿サイトだったか。
思い出しながらスマホをそうさし、やつの作品を画面上に表示させる。
○×賞、佳作とすでにトップ画面に表示されていた。
完全に、やつに先を越された。夢にまでみていた書籍化、やつが先に叶えた・・・
ふと、やつの投稿画面をさらに見ていると、思いがけない文字が目に留まった。
「クソ小説を読ませるな。つまんねぇよ」
なんだこれ?
よく見ると、やつの小説に対するコメントの一つだった。
他にも見てみると、普通の応援コメントに交じって、ひどいコメントがたくさん寄せられている。
中には「こいつはブス。絶対根暗な性格だよね」など、関係ない人格攻撃までしているユーザーもいた。
ネット民の軽口とはいえ、ぼっと怒りの感情が沸き起こる。
「こいつはかわいいぞ!知らねぇのか?」
気づいたらそんなコメントを返信していた。
まったく、我ながら何をやってんだか・・・
一気に冷めて、おれはカフェの店内に戻った。
「私、かわいいの?」
席に戻ると、なんともいえない表情のやつが、ぎこちなく笑いかけてきた。
「え、ああっ!?」
ソッコーでおれの返信コメントを読んだらしい。気まずくなりながら、椅子に座る。
「お前のコメント、荒らしもいるのな」
「見てくれる人が多いとね。中にはそういう人もいるよ」
「・・・むかつくな」
「そう?私は慣れたよ」
やつは、少し寂しそうに笑った。
「小説書くことってさ、どぶ川に沈むようなもんだよね。書いているうちは楽しくて、最高傑作が書けた!と思っても、ネット上に投稿したら批判され、コンクールに応募しても落選するしさ。たまに、何で書いてるんだろうって思うよ」
脳天気に見えたやつも、こんなことで苦しんでいるのか。
おれは意外に思うと同時に、近くにいながらもどこか遠くに感じていたやつが、とても身近に感じた。
いや、この感情は身近という表現だろうか?
「知ってるか?おれの特技は、素潜りとどぶさらいなんだ」
少し驚いたように、やつはおれの顔を見る。
「お前の周りが汚くて汚れてても、おれはそれをきれいにして、沈んでいくお前の手を引っ張りあげてやるよ」
やつは、くすっと笑う。
「私、水泳部だけど?」
「それでも沈むんだろ?」
「私より泳ぎうまいわけないじゃん」
「気合いで引き上げるんだよ」
「何それ、どういうこと?はっきり言って」
「だから・・・あーっ、もうあとはかってに想像しろよ!妄想は得意だろ!」
「お互いにね」
ふと、互いの視線がぶつかる。
お互いに声を立てて笑ってしまった。
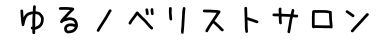
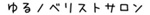


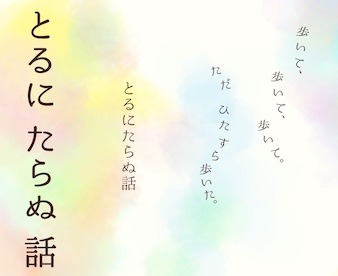





コメント